高次脳機能障害になって2年と5か月目|障害になることで得たメリット
脳に障害を負うと回復までが長いですね。本当にそう感じています。
精神的な部分の変化はまるでジェットコースターのようです。かなり頻繁に上下しています。「不安定」なんですね。心が。
なぜ不安定になるのかというと、土台となる部分があやふやになっているからだと考えています。
土台になる部分って何?って思うでしょう。人によって違うと思いますが、人に役立ちたいとか、何かに所属したいとか、そういう部分が満たされているかどうかなのではないかな?って考えています。
その土台を支えるのが、高次脳機能なんだと思います。遂行機能とか注意力とか記憶力とか…そういうやつ。
下のピラミッドの絵は、高次脳に関係している方なら目にしたことがあると思います。↓
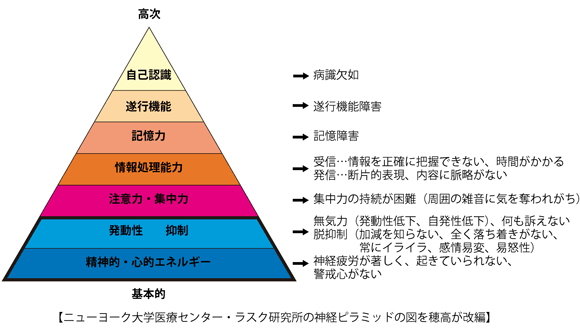
このピラミッドでは最上位に「自己認識」が据えられています。平たく言うと「障害の自覚」ってやつにあたるのかな?って考えています。
私がこの領域にたどり着くまで2年近くかかったんですよね。とても長かったです。
早い段階から頭では「自分は高次脳機能障害だ」とは認識していたのですが、本当の意味で自己認識が完成するまでは2年かかったってわけです。千葉リハのリハビリも当事者をこの領域に到達させるのが目的なのだと思います。
高次脳機能障害克服の第1目標は自己認識
思うんですよね。リハビリセンターでの高次脳のリハビリで対応可能な範囲って「自己認識」=「病識を持たせる」までなんだって。
それ以降はリハビリでは対応が無理なんだと思います。だって障害って困り事が問題の大元ですから。困らなければ障害ではないんです。
「日常生活の中で何をして困るのか」なんて、リハビリセンターの中では分かりませんものね。実際の生活の中で不便さを感じない事にはフォローのしようがありません。
例えば私がエンジニアです。屋内で作業しています。外で力仕事をする必要はありません。外で一日中動き回る体力がなくても困らないのです。でも職業によっては困る人もいます。その違いですよね。
私には記憶障害がありますが、お金をたくさん持っていて、毎日好きな事だけしていていいのであれば、別に記憶が悪くたって構わないんです。
もし「日常生活を送るうえで困ることがない。」だったら「障害はない。」になるんですよね。例えばお金が沢山あって働く必要が無いのなら、別に今の障害が一生残っても困らないのですよ。
でも現実はお金がないです。働かなければなりません。それなのに記憶が悪いようでは困りものですよね。記憶って無理にしようとしても出来ないものなんですよ。記憶が悪いとやるべきことを忘れてしまうんです。どんなに頑張って暗唱しても忘れます。常人にはわからない辛さがあります。なかなか厄介ですよコレ。
記憶に障害があると注意すべきことも忘れてしまいます。これは注意障害と診断される原因です。私は元々注意力が高い方でした。でも記憶障害の影響で注意すべきことを忘れてしまいます。だから注意障害とされているんですよね。困ったものです。
ここで大事なのは「日常生活で何に困るのかをはっきりと認識できること」なのだと思います。それは障害の自覚です。リハビリセンターでのリハビリのゴールなのです。
千葉リハでのリハビリのゴールは障害の自覚です。
障害の自覚とは障害を物理的に無くすことではありません。少しずつ改善しますが障害は残ります。治らないから障害なんです。
でもやり方によっては、障害による不便さを工夫でカバーできます。その知恵を学ぶのがリハビリセンターの存在意義なのではないかな?と思います。
高次脳機能障害は自己認識してからが本当の闘いの始まりだ!
障害が残っているとしても工夫でカバーできるようになる。人の手を借りなくても一人で行動ができる。これって「自立」なのだと思います。リハビリセンターでのゴールだと思います。
でも、現実は違います。ゴールには達していないと思います。ここからが第2幕の始まり。そのように感じています。
私が考える高次脳機能障害の第二幕を言葉にするとこうでしょうかね。
「人の上に立って人を導けるようになる。」
…やたらと大きな風呂敷を広げたようですね。「ちょっと大きく書きすぎたか?」なんて焦っています。でもまぁこのぐらいインパクトがあったほうがおもしろいので、そのまま書いておきます。
高次脳機能障害がこの大風呂敷にどうつながるのかを説明しますね。
まずスタートは「高次脳機能の最上位である「遂行機能」が万全に働くようになることです。」これってリハビリセンターでのリハビリのゴールです。
遂行機能が正常に働くということは、「失敗をしなくなる」ということなんだと思います。
記憶障害の場合だと「すべきことが頭から抜け落ちていた」ってやつがなくなる。ちゃんと予定通りに目的を果たせる。そういうことです。
で、失敗が減るということは「自分の行動に自信が持てるようになる」わけなんですよ。
私は障害を負ってから、散々なまでに叩きのめされました。叩きのめしたのは他人ではなくて自分自身です。とにかく行動を失敗するんですよ。記憶障害-注意障害-遂行機能障害の3コンボが毎回発動するんです。
もともと自信家だったのですが、障害を負ってからは完全に自信を喪失してうつ状態になっていました。作話なのか幻覚なのかよくわかりませんが、そういうものを見るほどまでに自信喪失です。常識ではあり得ないレベルの自信喪失です。
でも記憶力が戻るにつれて…そして記憶障害をカバーする工夫を重ねてきた結果、初期の頃に犯していた失敗は一気に減りました。今も記憶障害に起因する失敗はありますが、以前のような致命的なやらかしはありません。なんというか健常者時代に近い結果を残せているのではないか?と考えているほどです。
もはや記憶障害は克服したのではないか?と感じるほどです。(でも大変ですけれどね)
記憶障害があっても失敗しなくなるとどうなるか?
さて、こうして成功体験を積み直しすることで生じてくるのが自信です。
自信が付くとどうなるでしょうか?私は「積極的になれる」に続いていると思います。
行動をとれるようになるわけです。今までは「何をするに怖い。」という気持ちが先にありました。毎朝仕事のPCの前に向かうだけで吐き気の嵐でしたから。
それが解消する。失敗をしなくなる。すると心に余裕ができ始めます。積極的になれるんです。
なにせ行動をしても失敗しないわけですから、安心して行動にうつせるというものです。
行動がとれるようになれば締めたもの。というか、ここまで来たら健常者と変わらない状態だと思います。ここから先はさらなる高み。
健常者と同じレベルになったといっても、私は障碍者です。障害というものを経験してきています。これって裏返すと「普通の人が知らない世界を経験している」ということです。
ある意味、世界が広い。視野が広い。経験値が高い。こんな状態になっているわけですよ。
これ、考えようになっては武器にならないでしょうか?普通の人には絶対に持てない生きていくうえでの武器です。特別なスキルともいえるでしょうか?
障害者ゆえの有利さを活用したい
「障害者ゆえの有利さ」なんて書いたら「何を言っているんだこいつは?」って思う人もいるかもしれませんね。でも、世界が広がったのは事実なんですよ。
中途障害って、福祉の目から零れ落ちやすいです。健常者でもないし障害者でもない中途半端な存在なんです。世間からは「頑張ればできるのでは?」「怠けでは?」「甘えでは?」なんて厳しい目にさらされています。
でも本にからすれば明らかに障害をかかえているわけで、見た目が健常者そのものであっても「できないことはできない」状態なんですよね。
でも、もしこの中途半端な状態を克服できたとしたらどうでしょう…。工夫で乗り切って健常者に負けないレベルの生活が送れるようになったら…。
「自らをもって障害を知っているが、まるで健常者のように行動できる。」これって素晴らしいと思いませんか?思うのは私だけかなぁ…。言い換えれば「痛みを知っている人になれる。」なんですけれどねぇ。
この状態で人の上に立てるような。人を導くようなことが出来たら…とても素晴らしいと思います。
大変レアなケースだと思いますし、ユニーク性(他に同じことをする人がいないってことです)が高いです。
実際に障碍を武器に戦う人を見ました
「障害を武器に戦う」なんて表現すると「卑怯者」みたいにおもわれるかな?と思いましたが、障害を活用してはならない。なんてルールは誰が決めたのでしょうか?障碍者は弱々しくして病院の隅でおどおどしていなければならないのでしょうか?
そんなことは1㎜もないはずです。「障害者こうあるべきだ」なんて人権無視も甚だしいです。とんでもない差別ですよ。優生思想につながりそうです。恐ろしい!
というわけで、私は「障碍者が障害を武器に戦うのは大あり」だと考えています。「野球が得な人がプロ野球選手になるのは差別につながるから反対だ」なんて言う人はいないでしょう。それと同じですよ。自分の特性を生かしているだけですから。
私としては「脳波回復する」の著者の方が、高次脳機能障害を武器に戦う人の一人なのだと考えています。本まで出して活動しています。凄いと思います。尊敬します。
実際に会ってお話をしたことがあります。その後1回か2回ほどネットで対談をしたかな?その後も対談の予定があったと思うのですが、その後、特に進展もなく…って感じですが(笑)
私も、相手もお互いに高次脳機能障害ですから、なかなかレアでヘビーな状況だと思います。インタビュー中に調子が悪くなるのか、停止ボタンを押したかのように相手の時が止まってしまったりもしていましたが、それはそれでアリです。ゆっくりまったりと脳が再起動するのを待てばいいだけですし。
高次脳の方の行動は千葉リハでもさんざん見てきましたから、すべて私の許容範囲内です。私自身もどこで何をやらかしているか…ですしね!
多少段取りが悪くても大丈夫。全く気にしません。私もエンジニアでIT機器を使って仕事をしています、操作ミスや機器の具合で、想定外の事が起こるのは慣れっこです。私の経験上「本番時にIT機器が正常に働くのは稀である。」という認識です。
高次脳機能障害になった結果、良い方へ考え方が変化しました。
私って生粋のエンジニアです。数値が1ずれたら成り立たない世界にずっと住んでいました。
パソコン歴=プログラミング歴=40年の歴戦の猛者だと認識しています。ここまでITの世界にどっぷりだと、それはもう神経質そうなイメージを持たれるかもしれません。実際そうだと思います。
私は言葉の端々とか、数字とか、めっちゃ細かい所が気になります。矛盾した行動とか発言とかされると「うわあああ。何を言ってるんだ!なんて非効率なんだ!」とか「もっとはっきりとした情報じゃないと判断が付けられないよ!」と混乱する傾向がありました。ゼロかイチかの考え方が強かったんですよね。
でも今はだいぶ考え方が変わってきています。相手の失敗はあまり気にしなくなりました。なにせ私の方が大いに失敗しまくっていますから。人のことは全く言えなくなりましたし。
それにさんざん周囲に助けられていますから。それこそ周りが失敗しようものなら「恩返しのチャンスだ!」とばかりに助けたいと考えるようになりました。自分を認めてもらう良い機会にもなりますし。
というわけで、私は高次脳機能障害な自分そのものについては「新しい世界も経験できているし、まぁこんなもんだろう」的なスタンスです。
既存の仕事も周るようになりましたし、新しい仕事始めたとしても「そこそこ活躍できるようになるはずだ。」と、自分を信じられるようになりました。
あとは、「この高次脳機能障害の体験談ブログのアクセスがもっと増えたらいいのになぁ」ってところでしょうか。
これからは、現状を維持しつつ、新しい行動を少しずつ増やす。けして停滞はしない。
そんな感じで完全復帰を目指す。というか、病前の自分を超えたいと思います。
今後の課題は「夕方になると記憶がどこかに行ってしまう。」ことへの対処からですかね。
なかなか手ごわいですよ!


